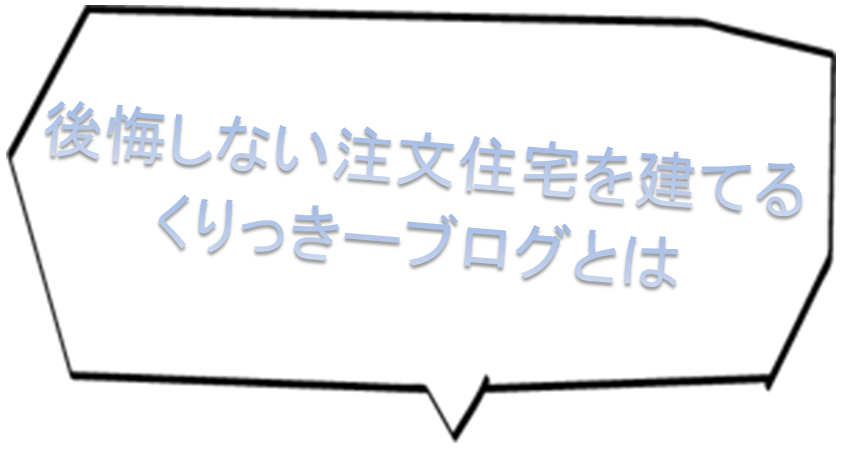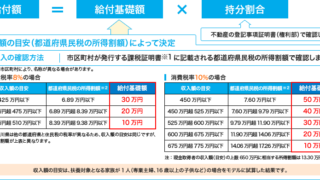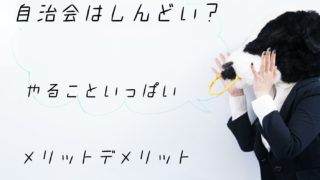以前の記事で玄関の上がり框(かまち)の高さのメリット・デメリットについてを書きましたが、今回は上がり框(かまち)の段差の理想の高さについてを考えていきたいと思います。
以前の記事は、こちらをご参考ください。

玄関上がり框(かまち)の段差の高さについて
まず上がり框とは、
上がり框とは、玄関などの上がり口の間口方向に取り付ける横木のこと。ケヤキなど木目の美しい木材のほかに、人造大理石や御影石なども使われている。
上がり框の段差は高くても低くても、それぞれメリット・デメリットがあります。
若くて元気なときには、上がり框の段差が高くても低くてもそれほど気にせずに対応できます。
しかし高齢になるにつれ、下肢の筋力も低下してきますので段差の高さが重要となってきます。
高齢になると、靴の着脱を立ったまま行うのがつらくなってくる可能性もあります。(土間が広ければ椅子を置いておき、そこに座って靴の着脱を行うという方法もあります。)
今回は、靴の着脱を上がり框に座って行うとします。
上がり框の段差の理想の高さを考えるとき、段差の昇降動作と段差の立ち座り動作の行いやすさを考慮する必要があります。
玄関上がり框(かまち)の段差昇降動作
まず上がり框の段差昇降動作から考えていきます。
上がり框の段差を上がるときも降りるときも、当然段差が低ければ低いほど行いやすくなります。
ただ段差を低くしすぎてしまうと、段差に対しての意識が薄くなってしまうので逆につまづきやすくもなります。
また段差を低くしすぎると、次に書く立ち座り動作が行いにくくなります。
国土交通省が公表している『高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(平成24年)』によれば、高齢者・障害者に配慮した階段の蹴上げは16㎝以下とされています。(一般的には建築基準法で蹴上げは23㎝以下とされています。)
蹴上げとは、一段の高さのことです。
玄関上がり框(かまち)の段差の立ち座り動作
上がり框の段差の立ち座り動作では、段差が高いほど行いやすくなります。
一般的には座ったときに、膝の位置よりも臀部の位置が少し高めになっていると立ち上がりやすくなります。
ただそのように上がり框の段差を高くしすぎると、先に書いた昇降動作が行いにくくなります。
また高齢になると10㎝以下の高さからでは、手を使わずに立ち上がるのは難しくなってきます。(ロコモ立ち上がりテストでも10㎝の高さから立ち上がれない高齢者は多い。)
玄関上がり框(かまち)の段差の理想の高さ
上がり框の段差の理想の高さは、それの使い方や対象者によって異なりますのでなかなか考えにくいものです。
ただ若くて元気なうちには上がり框の段差の昇降動作や立ち座り動作で身体的に苦労することはないと思います。
となると、上がり框の段差の理想の高さは、高齢になったときに段差の昇降動作や立ち座り動作が少しでも楽になるように設定しておくのが良いと思います。
昇降動作が行いやすい上がり框の段差の高さは、高齢者に配慮した段差16㎝以下とします。
立ち座り動作を行いやすくするには、段差を最低でも10㎝以上にしておきたいところです。
以上を考慮すると、私が考える上がり框の段差の理想の高さは10㎝~16㎝となります。
老後の上がり框については、こちらの記事にも書いていますのでよろしければご参考ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。